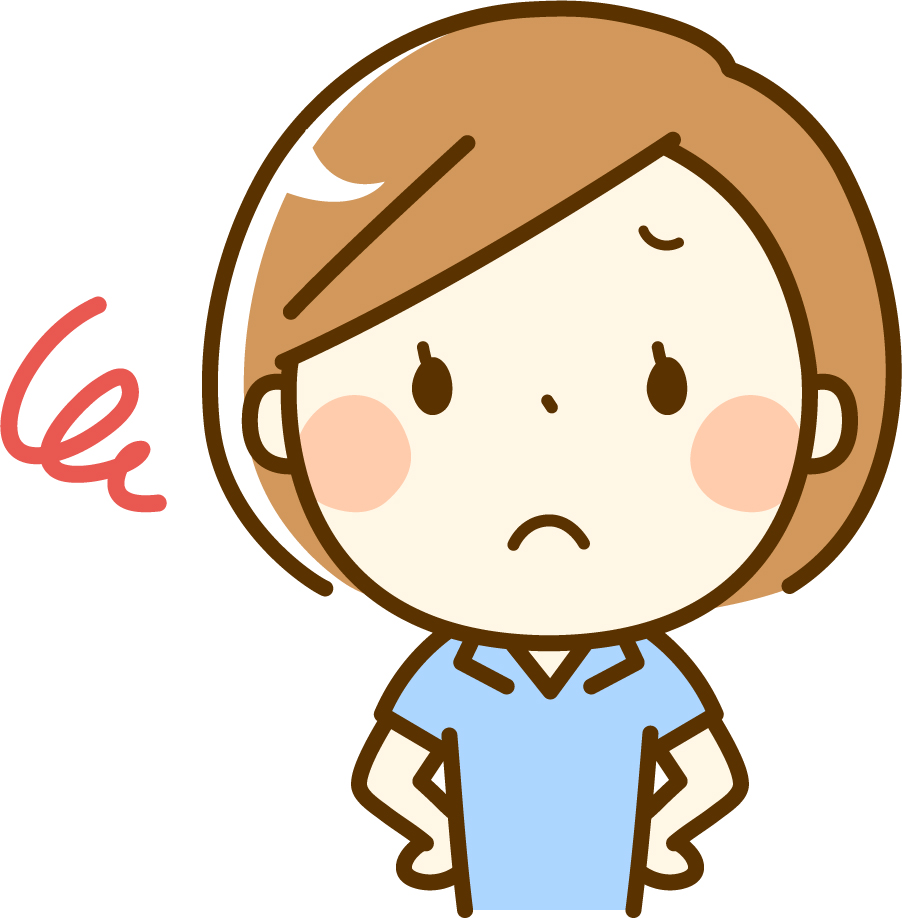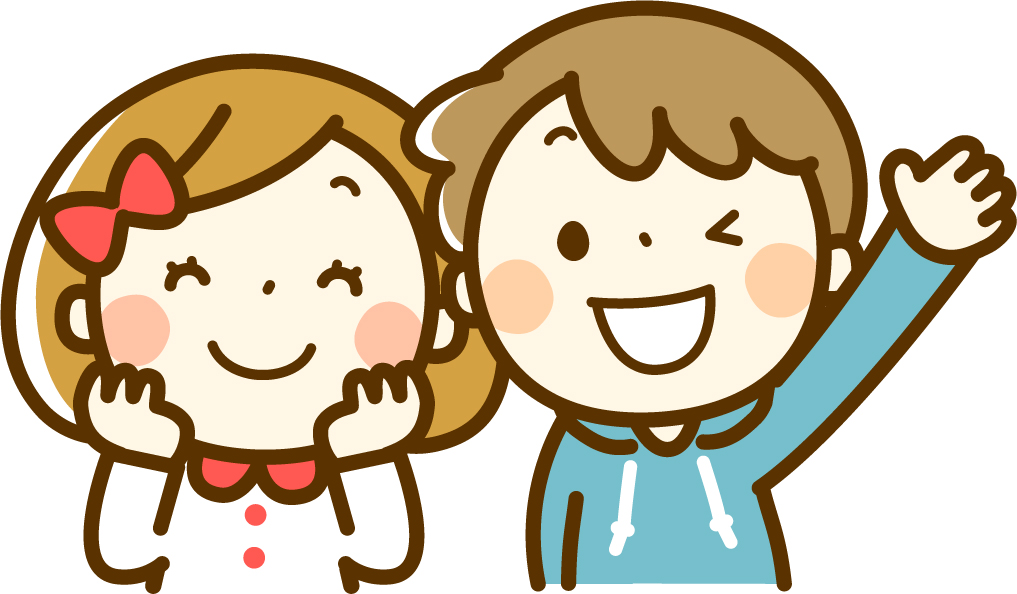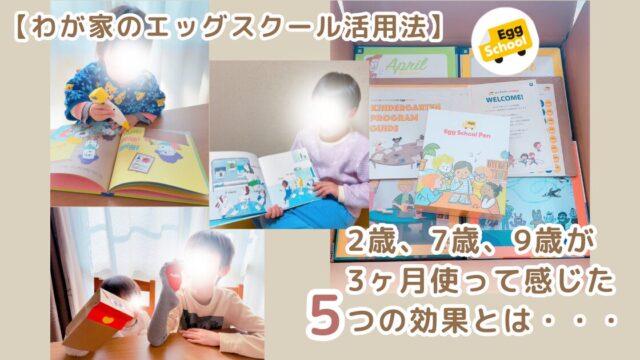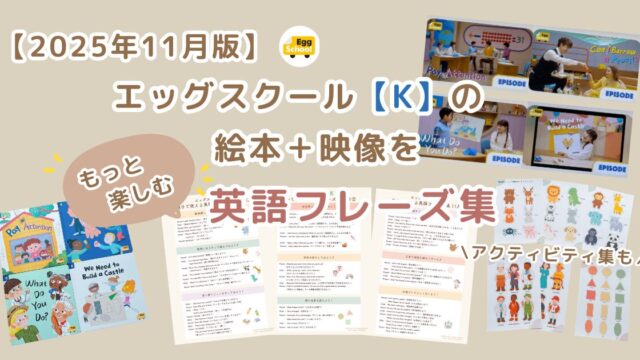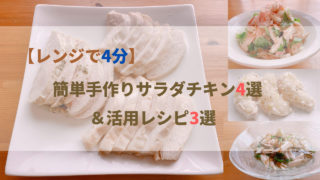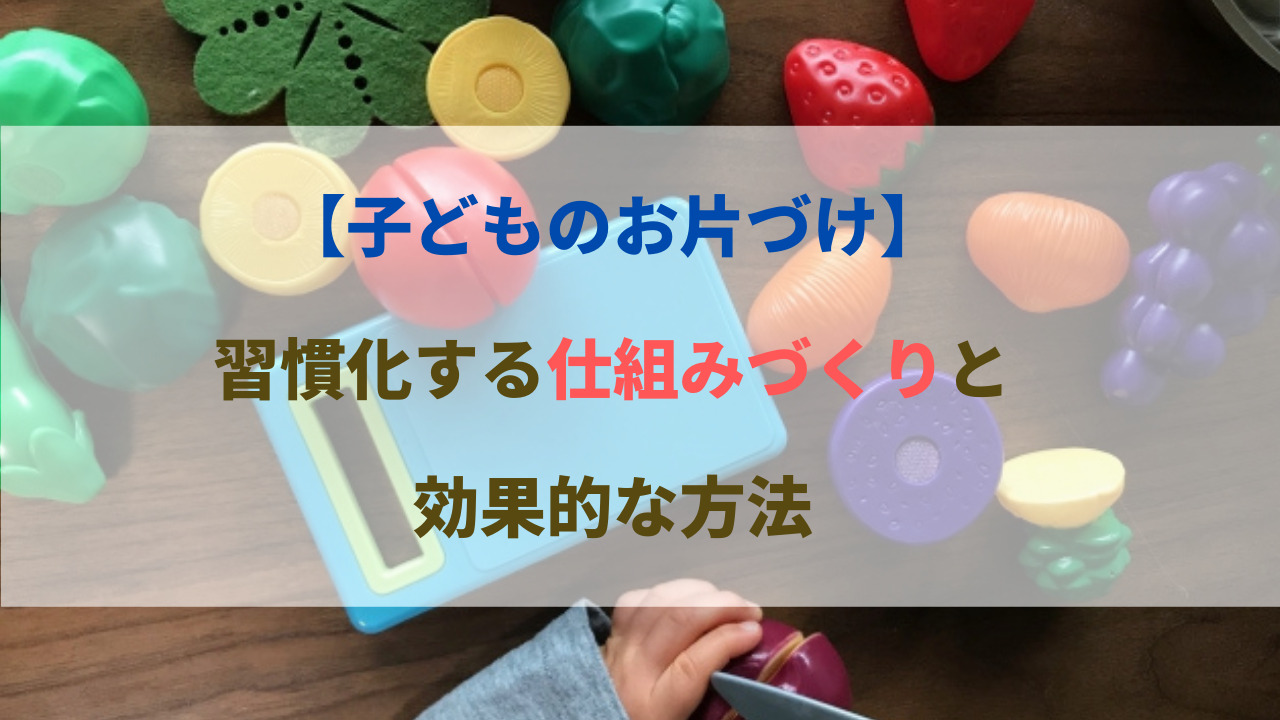
こんなお悩みはありませんか?
・子どもがお片づけしやすい仕組みづくり
・子どもにお片づけをしてもらう効果的な方法
こんにちは、ぽんきちです。
今回は、子どもにお片づけをしてもらうために、簡単にお片づけできる仕組みづくりと子どもにお片づけしてもらう効果的な方法をご紹介します。
”おもちゃで遊んだ後はきちんとお片付けしてほしい”
というのは誰しも親なら子どもに抱く望みですよね。何を隠そう私自身が、切にそう望んでいました。
わが家には、5歳息子と3歳娘がおります。
”どうやったら子どもがお片づけしてくれるかな”と考え、色々な本を参考にしたり、自分なりに試行錯誤したりしました。
そこでわかったのは、子どもが自分で片づけができる仕組みづくりさえしてあげれば、子どもはちゃんとお片づけができるということでした。
実際、我が家では片づけの仕組みづくりをしたお陰で、子どもたちが遊んだ後に合わせてお片付けまでしてくれるようになりました。
お片づけがきちんとできる習慣が身につけば、ママ、パパの負担が軽くなるのはもちろんのこと、身の回りを整えるという子どもにとって一生役に立つ「生活力」を身につけることができます。
是非、子どもに楽しく、お片づけを習慣化させてあげましょう!
子どもがお片づけしやすい仕組みづくり

まず大切なのが、子どもが「使いやすい」「片付けしやすい」ような片づけの仕組みづくりです。3つに分けてご紹介していきます。
①適量を決める
まずは、収納スペースに収まる「ちょうどよい物の量」を決めます。
この時に勝手に親が捨てるおもちゃを選ぶのではなくて、子ども自身に選んで決めてもらうことが大切です。
私が実践したのは、
- 子どもと一緒に、全部おもちゃを出す
- 子ども自身に、”使っているもの”と”使っていないもの”にわけてもらう
- 収納する場所の7~8割の物量を目指す
全部おもちゃを出すことで、子どもにも”こんなにたくさんおもちゃあるんだ”ということを感じてもらうためです。
その上で、『収納スペースに収まる分があなたのおもちゃだよ』と、子どもが自分で無理なく管理できる量を把握できるように導いてあげます。
いる・いらないで分けようとすると、なんでも『いるー!』と言われそうなので、我が家では、使っている・使っていないというものさしで分けるようにしています。
はじめの頃は、使わないおもちゃを選ぶのに時間がかかっていた子ども達。でも最近では、あっという間に選んでくれるので、私の方がびっくりしています。
「選別」も繰り返すことで、判断力が上がり、物に対する価値観が鋭くなっていると実感しています。自分なりの判断基準ができてきたようです。
「今使っているものが残すもの」という意識を持たせることで、上手にものを手放せるようにもなってきます。
そして、物の量は収納するスペースの7~8割を目安に。多く物を持ちすぎると、それに伴い、片づけも大変になりますよね。
②定位置を決める
おもちゃの「ちょうどいい量」がわかったら、それらの定位置を決めていきます。
定位置を決める時に意識したこと
・遊ぶ場所に近い所に収納する
・子どもでも収納場所がわかるようラベリングする
できるだけ、子どもたちが普段遊ぶ場所の近くにおもちゃの定位置を決めたのは、少しでも片付ける時が楽になるからです。
またラベリングは、文字で書いたり、写真を貼ったりと方法はありますが、わが家では3歳娘がまだ字が読めないので、おもちゃの写真を貼って視覚的にすぐわかるようにしました。


ダイソーの積み重ねBOXを使用。写真を小さめに印刷し、両面テープで貼るだけです。
以前に、子供たちに『お片づけをしてね』とお願いをした際、ほとんどはきちんとお片づけできたのに、1つだけ片付けられないものがありました。
それは、まだ定位置を決めてなかった最近新しく買ったおもちゃでした。
子どももきちんとおもちゃの定位置を決めてあげれば、お片付けできると実感した出来事でした。
③取り出しやすく、戻しやすいを意識する
おもちゃの定位置は、子どもが取り出しやすく、戻しやすい場所にすることが大切です。
ちょっとしたやりづらさがあるだけで、子どもはおもちゃを「元に戻す」ということをしてくれなくなります。
取り出しやすく、戻しやすくするためにしたこと
・1アクションでお片付けできるように、フタをなくす
・子どもが片づけの際に戻しやすい高さに収納する
・ザックリ片づけれる何でもボックスを作って、細かく分けすぎない
フタがあるだけで、遊ぶ時にも片付けの時にも開け閉めの動作が多くなります。
そうなると、子どものお片づけのハードルが上がってしまいますよね。

次に、子どもの目線の高さまでに遊ぶおもちゃを置くようにしました。
おもちゃが高い所で取り出しにくいと、あまり遊ばなくなったり、きちんと戻してくれなかったり。片づけするのが面倒に感じてしまいますよね。
最後に意識したのが、細かくわけすぎないということです。
1つ大きめのなんでもボックスを設置し、小さな細々したものは、そのボックスにお片づけすればOKというゆるいルールです。
子どもにお片付けしてもらう効果的な方法

ここからは、実際にわが家で試してみて効果のあった”子どもにお片付けをしてもらう方法”をご紹介していきます。
片づけをゲーム感覚で楽しむ
子どもたちは、ゲームや競争が大好き!
『おかちゃんとどっちが早くお片づけできるかな?よーい、ドン!』というと、『〇〇ちゃんが勝つぞ~!負けないぞ~!!』とやる気満々で、一生懸命お片づけを頑張ってくれます。
少し手加減して子どもに勝たせてあげると、『やったー!勝った!』と子どもは大喜び。
そして、ママもお部屋すっきり大喜びです(笑)
他にも、時間を決めてお片づけをするのもオススメです。
タイマーを5分にセットして、『ピピッとなるまでにお片づけできるかな、まだ難しいかな』と子ども心をくすぐる作戦です。
『できるよ、簡単よ!おかちゃん、見んといてよ~!』と言いながら、二人で走りながら急いでお片づけをしてくれます。
そして、『見ていいよ~♪』といった時の誇らしげな満足顔。
ここで、大げさに『すごいねぇ!!全部きれいに片付けてくれてる!おかちゃん、嬉しいな。ありがとう!』としっかり褒めてあげます。
「どうしてお片づけをするのか」きちんと説明する
お片づけを楽しいと思ってもらえたら、どうしてお片づけをするのかを自分なりに子どもに伝えるように心がけています。
例えば、
お片づけできてたら・・・
・『すぐに遊びたいおもちゃが見つかるよね』
・『広いスペースを使って遊べるよね』
・『おもちゃを踏んで壊すこともないよね』
・『おもちゃもお家に帰れて嬉しいよね』
というような声がけです。
お片づけをすることがどうして大切なのかを、子ども自身が考えて理解することで、子どもも自らお片づけしてくれるようになります。
お片づけした後の「気持ちよさ」を実感してもらう
子どもが頑張ってお片づけをした後は、
『片付けるとスッキリして、気持ちいいね!』
『おもちゃもお家に帰れて喜んでるよ。』
と、お片づけして良かったことを子どもに言葉で伝えています。
視覚的にもキレイに片づいたお部屋を見て、子ども自身にも「お片づけしたら気持ちいいな」と感じて欲しいからです。
そして、子どもが片付けを頑張った後には必ずたくさん褒めてあげます。
『ありがとう、すごくキレイになったね』
『〇〇ちゃんのおかげで、ママもとても助かったよ』
子どもは、パパやママが喜んでくれるのが大好き!
子ども自身でお片づけをする気持ちよさを感じてもらい、お片づけはパパやママにも喜んでもらえると思えば、また進んでしたくなりますよね。
こうした日々の積み重ねで、お片づけが好きになってくれて、自分から積極的に動いてくれるようになれば最高です。
まとめ:子どものお片付けを習慣化しよう!

今回は、子どもがお片づけしやすい仕組みづくりと子どもがお片づけをしてくれる効果的な方法をご紹介しました。
最初はうまくできなかったお片づけも、きちんと仕組みを作ったうえで、子どもに声がけをしながら繰り返していくといずれ習慣となっていきます。
「片づけ」は、大切な生活習慣の1つ。
子どものうちから身につけていれば、一生モノの宝になるはずです。
親子で楽しみながらお片づけの仕組みを作り、楽しい声がけや片付けやすい工夫で、お片づけが習慣化できるといいですよね!
少しでも、今回の記事が参考になると幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
ブログ村のランキングに参加してます。
☟ポチッと押していただけると、とても励みになります。